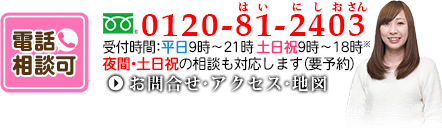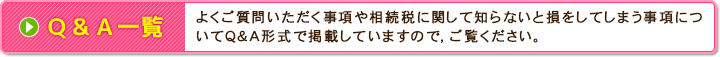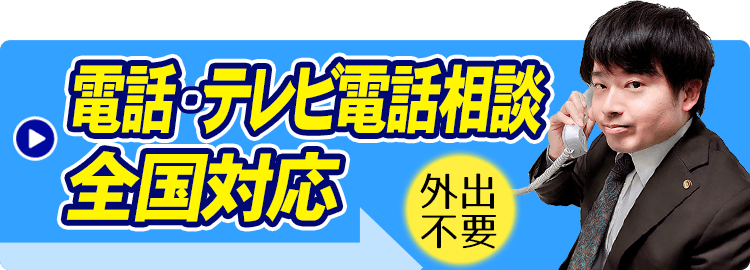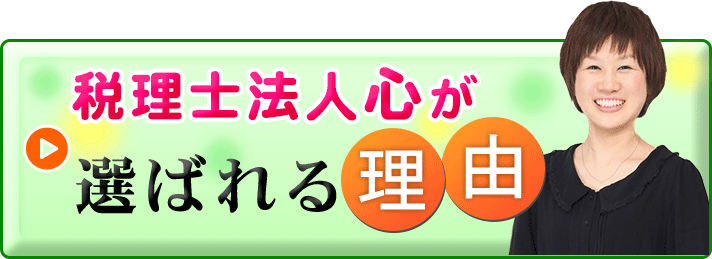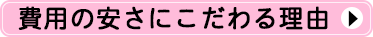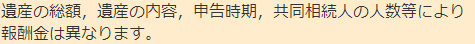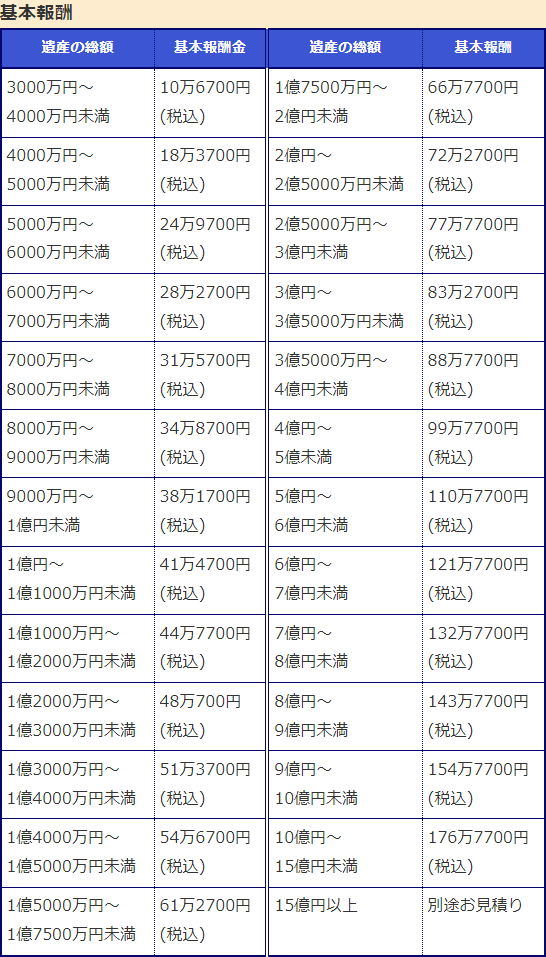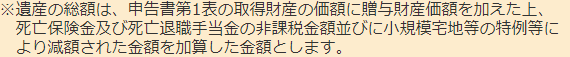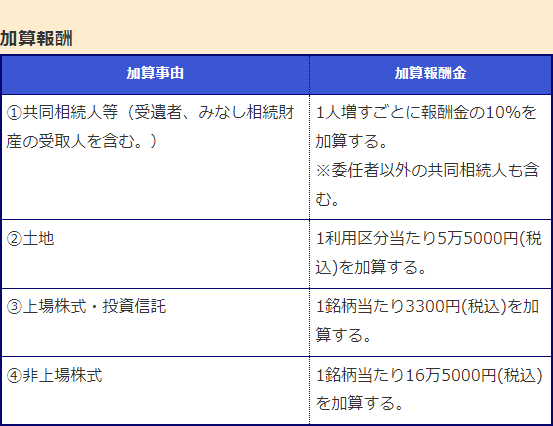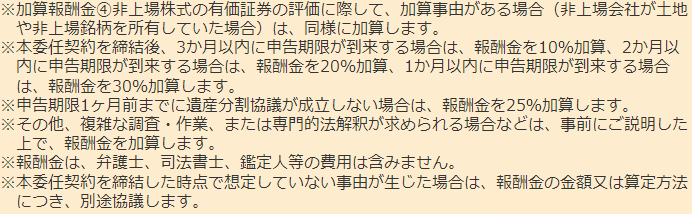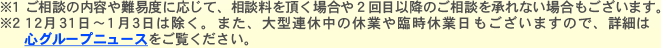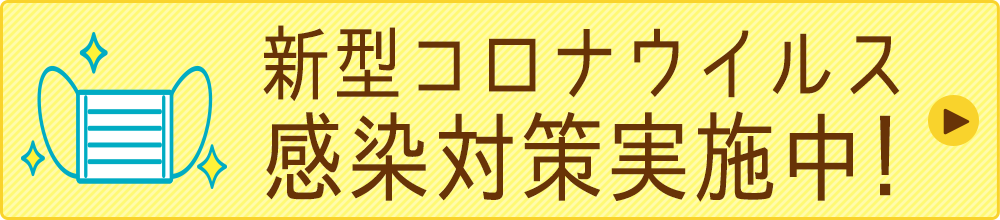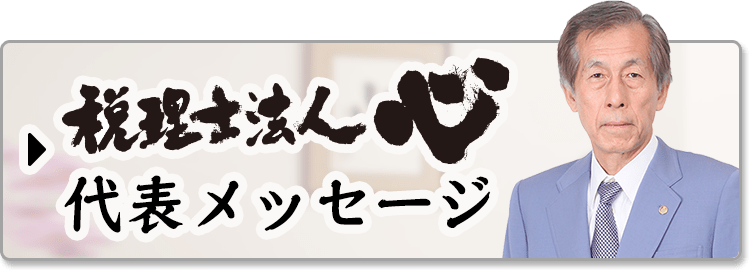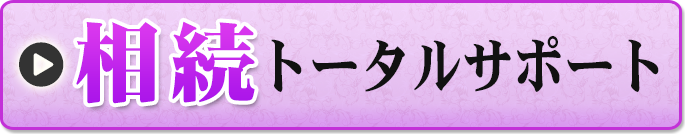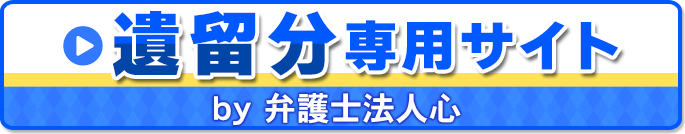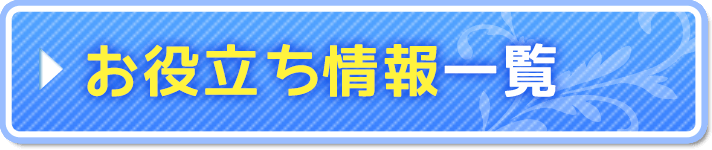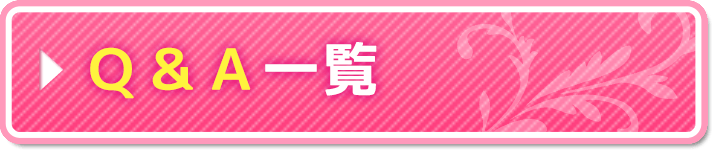お役立ち情報
相続税の基礎控除額
1 基礎控除額とは
相続税の申告が必要かどうかを判断する際には、相続によって取得した財産の額が基礎控除額を上回っているかどうかをまず初めに検討します。
相続によって取得した財産の額(相続の際に財産を取得した場合のその財産の課税価格の合計額)が基礎控除額よりも少ない場合には、相続税の申告の必要はありません。
多くのケースで財産の額がこの基礎控除額の枠内に収まるため、申告の必要のない相続がほとんどであるといえます。
2 基礎控除額の計算式
平成27年1月1日以降の基礎控除額の計算式は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。
それ以前の基礎控除額は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」となっていました。
平成27年以降に相続が開始された方については、相続税の申告が必要である可能性が高くなっておりますので、ご注意ください。
3 養子がいる場合の基礎控除額の計算
亡くなった方が養子縁組をしていた場合、基礎控除額の計算において法定相続人の数は増えるのでしょうか。
この点については、養子縁組がされた場合には、法定相続人の数は増えることになります。
しかし、養子縁組を行えばいくらでも基礎控除額を増やせることになるため、相続税法上は基礎控除を算出する際の養子の数に上限を設けています。
亡くなった方に実子がいる場合には、養子が何人いても、原則として1人までしか法定相続人の数に加えられません。
亡くなった方に実子がいない場合には、養子は原則として2人まで法定相続人の数に加えることができます。
4 代襲相続の場合の基礎控除額の計算
代襲相続の場合の法定相続人の数について、例を挙げてご説明します。
岐阜県に住み、配偶者に先立たれていた方が亡くなり、その方には長男と長女が2人いました。
長男はその方よりも先に亡くなってしまっており、長男には岐阜県外に子どもが3人いました。
このケースでは、長女と孫3人(代襲相続人といいます)が相続人となります。
基礎控除額の計算においては、代襲相続人全員の数を計算に入れられますので、法定相続人は合計4人として計算することができます。
5 相続放棄をする人がいる場合の基礎控除額の計算
上記の例のケースで、相続放棄の場合の法定相続人の数について考えていきます。
岐阜県外に住む孫3人は相続放棄をすることになりました。
相続放棄をした場合には、法的には相続人とならなかったことになりますが、相続税の基礎控除額の計算においては、相続放棄をした相続人についても法定相続人の数に算入することができます。
なお、遺産分割などによって、相続財産を取得しなかった相続人がいた場合にも同様です。