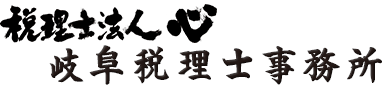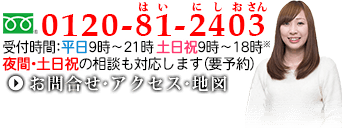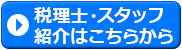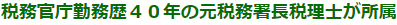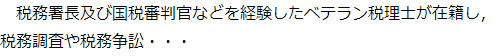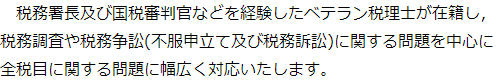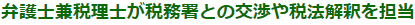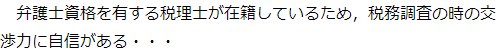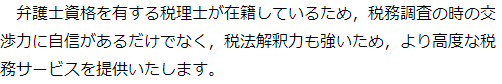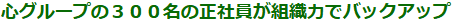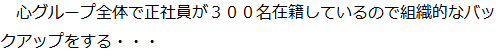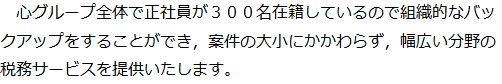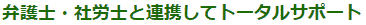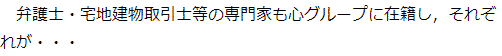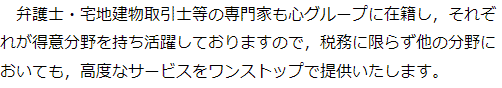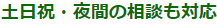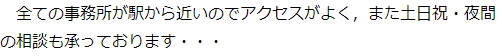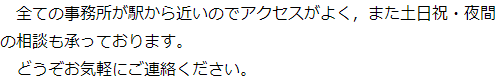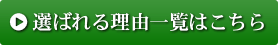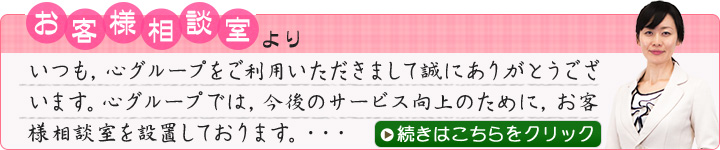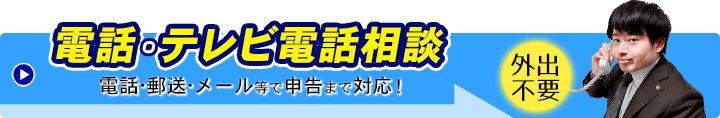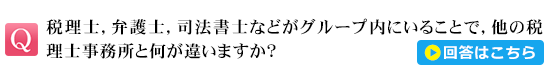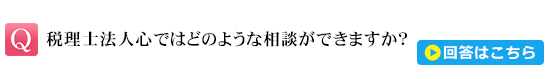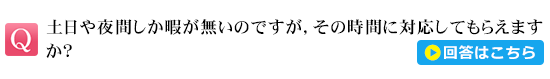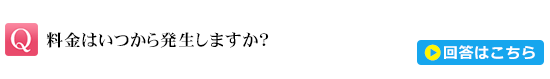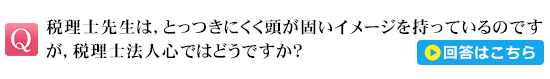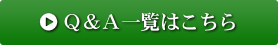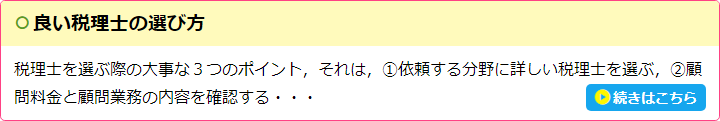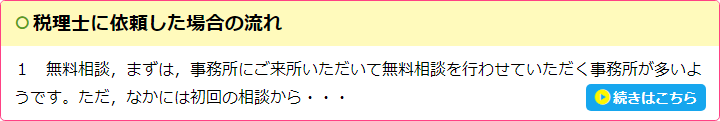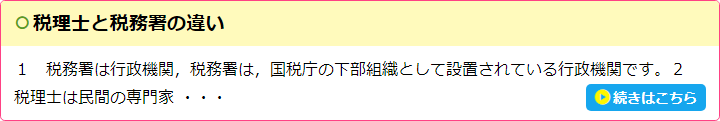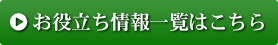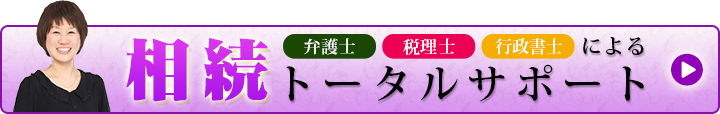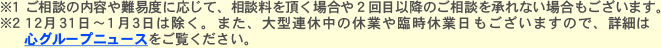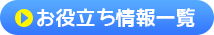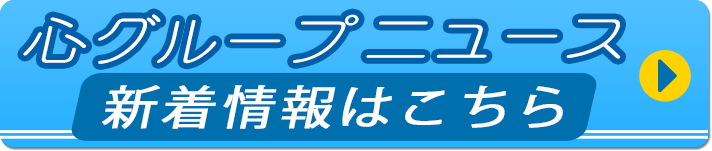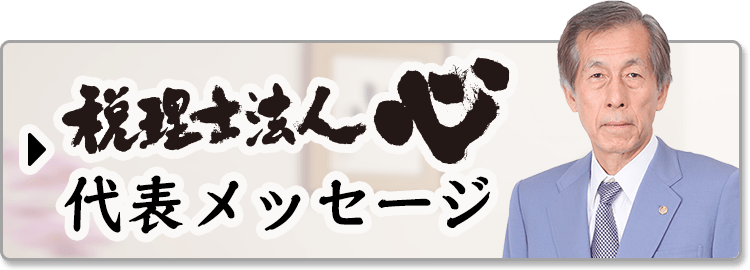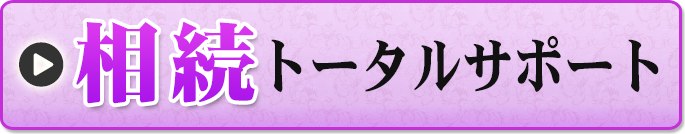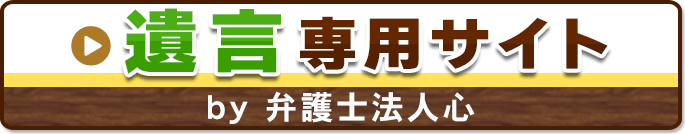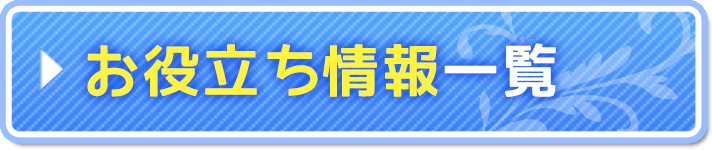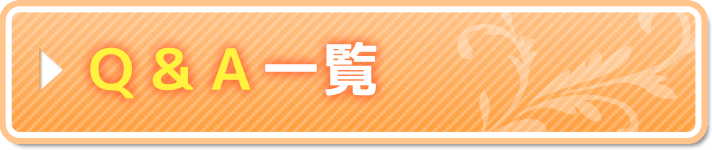税理士をお探しの方へ
税理士法人心 当事務所は利便性のよい立地にあります。所在地については、こちらをご覧ください。税に関するご相談に真摯に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
費用の安さだけで税理士を選んではいけない理由
1 税理士と費用

税理士を選ぶ際、費用の安さだけで選んではいけない理由はたくさんあります。
税理士報酬が安いということには魅力があるものの、それだけを理由に税理士を選んでしまうと、長期的に見て大きなリスクやデメリットが生じる可能性があります。
ここでは、費用の安さだけで選択することでどのような問題を引き起こすかについて説明していきます。
2 税務サービスの質が低下する可能性
税理士報酬が安い税理士は、コストを削減するためにサービスの質を下げざるを得ないことがあります。
例えば、人件費が税理士事務所の大きなコストの一つではありますが、業務量が多くても税務スタッフを増やさず、一人の税理士が多数のクライアントを担当することがあります。
このような場合、納税者に対する丁寧なサポートが行き届かなくなりかねません。
納税者の要望に対する対応が遅れたり、税務申告の精度が低下するリスクが高まります。
特に、複雑な税務処理が必要な場合や、個別の相談検討が必要なケースでは、質の低いサービスが原因で問題を引き起こすことがあります。
3 税務に関する専門知識や経験の不足
税務に関する法律は毎年のように改正される分野であり、最新の知識と豊富な経験が求められます。
安価な税理士報酬で対応している税理士事務所は、人件費を抑えるために安く雇える経験の浅い税理士や専門知識に乏しいスタッフを多く採用している可能性があるため、適切な税務アドバイスを提供できない可能性があります。
特に、相続税や法人税などの複雑な税務においては、専門的な知識が必要となるため、経験豊富な税理士を選ぶことが重要です。
税理士報酬の安さだけで税理士事務所を決めると、結果的に不適切な税務処理が行われ、後々税務署から指摘を受けるリスクが高まります。
4 税務調査でのリスク
税務調査は、税務署が過去の申告内容を確認し、誤りがないかを調べるための手続きです。
税務調査で誤りが見つかった場合、過少申告加算税や延滞税といった追加の納税が課されることがあります。
安すぎる税理士報酬で経験の浅い税理士が税務申告に関わる場合、詳細なチェックを行わなかったり、税務上の問題について十分な検討を行わず、申告内容に誤りが残る可能性もあります。
そういった場合には、結果として、税務調査でのリスクが高まり、節税効果を得られないばかりか、追加の納税を支払うことになるかもしれません。
税理士に相談すべきケース
1 税金と税理士への相談の必要性

資産家ではなく事業もされていない方の中の場合、ご自分が税理士とは無縁だと思っている方も多いのではないでしょうか。
もちろん、資産家や事業をしている方は、税理士に相談すべきことが多いのですが、そうでない方も税金と無関係でいられるわけではありません。
サラリーマンの方でも毎月、給料から所得税が源泉徴収され、年末には年末調整の手続きをすることになりますし、住宅ローン控除やふるさと納税のために確定申告をすることが必要になってくることもあります。
ここでは、税理士に相談すべきといえるケースについてご紹介いたします。
2 所得税と税理士への相談
サラリーマンで、一か所から給料をもらっている場合には、基本的には、年末調整の手続きをすることにより、確定申告を行う必要がなくなります。
ただし、住宅ローン控除をする場合は1年目に確定申告をする必要がありますし、メルカリで継続的に売買をしていたり、アフィリエイトで一定金額以上に収入を得ていたりする場合にも確定申告をする必要があります。
確定申告に不安がある方は、税理士に相談すべきです。
3 法人税と税理士への相談
法人の決算書を作成するには、税金に対する一定程度の理解と知識が必要となります。
また、毎月の試算表の作成、キャッシュフローの状況、経営の状況の確認、それに対する改善策を考える必要があります。
法人が大きくなれば大きくなるほど、そういった相談をする相手が必要になりますので、その相手として税理士に依頼することを検討されることをお勧めします。
4 相続税と税理士への相談
相続税の申告書を作成する場合には、相続財産を漏れなく把握し、不動産がある場合は、評価額を算出したうえで、相続税を算出する必要があります。
不動産の評価は、土地の形、周辺の状況、権利関係によって、評価額を算出する必要があります。
また、不動産については、特例の適用を受けることで、評価額の減額を行うこともできます。
財産の中に不動産がある場合には、税理士に相談をすることをお勧めします。
税理士法人心の強み
1 税金に関係する様々なサービスを総合的に提供できる

当法人は、弁護士法人、社会保険労務士法人などと一体的に連携しています。
例えば、税務顧問も頼みたい、給与計算も頼みたいということであれば、社会保険労務士法人と連携します。
また、相続税の申告と相続手続きの代行を併せて頼みたいということであれば、弁護士法人と連携します。
このようにご相談の内容に合わせ、総合的なサポートを実現できます。
また、士業・スタッフ合わせて多くのメンバーがいるため、必要に応じて組織的なバックアップが可能で、様々な税分野及び関連分野でのサービスを提供させていただきます。
2 税理士が多数在籍していることと専門性
当法人には、多くの税理士が在籍しているので、各税理士がそれぞれの得意分野の経験を高め、スキルを磨くことができます。
例えば、平均的な税理士であれば、年に数回の相続税申告しかしないため、相続税の経験を積みにくいといわれています。
しかし、当法人では、特定の税理士が集中的に相続税の経験を積むことができるので、相続税においてスキルを磨くことができます。
3 税理士兼弁護士が在籍
当法人には、弁護士資格をもっている税理士が多数在籍しています。
税理士兼弁護士は、税務調査の際の交渉力に長けており、より高度な税務サービスを提供いたします。
また、税理士兼弁護士の税法解釈力の高さが、提供できる税務サービスの質の高さにつながります。
4 土日祝日でもお客様のご都合に柔軟に対応します
当法人は、お客様の時間を無駄にしないために、駅から近いアクセスがよい場所に事務所を構えています
また、事前に予約していただければ、平日夜間はもちろん、土日祝日の相談も承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
税理士に相談する際の流れ
1 税理士相談の流れについて

税理士と普段関わりがある方であれば、その税理士に相談するにあたって特に戸惑うようなことはありませんが、普段は確定申告をしていないという方が、税理士に初めて相談するという場合には、戸惑うことが非常に多いのではないでしょうか。
ここでは、税理士に相談をする際の一般的な流れについて解説いたしますので、不安解消の一助にしていただければと思います。
2 予約と相談
まずは、予約をしていただいた上で、ご相談いただくことになります。
ほとんどの税理士事務所で相談の予約が必要と思っていただくとよいかと思います。
また、初回相談を無料としている税理士事務所もあれば、有料相談のみを行っている事務所もあるので、事前に電話をして、相談料について確認することをおすすめします。
3 ニーズの聞き取り
税理士は、お客様が何を求めているのか、ニーズを聞き取ります。
生前対策、贈与税の申告、所得税の確定申告、記帳代行、決算書の作成、税務調査対応等、ご希望される業務内容をお伺いします。
中には、どういったことを税理士に頼めるのか分からないという方もいらっしゃいますので、お客様のお話をもとにサポート内容をご提案させていただきます。
4 税理士の報酬の見積もり
ほとんどの税理士事務所では、見積もりを出してもらうことができます。
税理士によっては、事前に説明していない費用を後から追加で請求してくることもありますので、注意が必要です。
5 契約書作成
税理士の業務の範囲、税理士報酬の額について、納得いただけましたら契約書を取り交わします。
税理士の中には、契約書をしっかりと作成しないところもあるようですが、契約書を作成しないことはトラブルの元になりますので、必ず契約書を作成してもらうようにしてください。
税理士に依頼するタイミング
1 税理士への相談をお考えの方へ
税金問題で困ったときや不安なときは、まず税理士に相談するという方が多いかと思います。
ここでは、どのタイミングで税理士に相談し、依頼すべきかについて、ケース別に説明をしていきたいと思います。
2 所得税のことを税理士へ依頼するタイミング

所得税については、毎年1月1日から12月31日の収入と経費を集計し、翌年3月15日までに確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。
所得税の確定申告書は、簡単なものであれば、1週間から3週間程度の期間で作成できることが多いです。
しかし、事業を営んでいて取引が多い場合などには、さらに期間がかかりますので、基本的には1か月から2か月程度の期間が必要であることを念頭において、税理士に相談することをおすすめします。
ただし、申告期限の直前など税理士の繁忙期に依頼をしようとすると、断られる可能性もありますので、できるだけ早めに相談することをおすすめします。
3 法人税のことを税理士へ依頼するタイミング
法人税の申告期限は、決算日の翌日から2か月以内です。
法人税の申告書を作成するには、1か月から2か月以内の期間は必要です。
なお、法人は、取引が多くなる傾向にありますので、毎日の記帳が重要となります。
小規模な法人でない限り、1年に1回、領収書をかき集めて帳簿及び申告書を作成するというのはかなり大変な作業です。
法人の規模が大きいほど、早めに税理士に相談することをおすすめします。
また、申告の際に税理士へ依頼するのではなく、日々の記帳代行を依頼するという手段も考えられます。
4 相続税について税理士へ依頼するタイミング
相続税の申告期限は、相続開始を知った翌日から10か月以内です。
この期限までに、相続税の申告書の作成及び提出の上、納税もする必要があります。
相続税の申告にあたって必要な資料の種類は多く、申告書の作成には、1か月から3か月の期間を要します。
財産の分け方について、相続人同士の意見を調整する必要がある場合には、さらなる時間がかかることもあります。
そのため、相続税については、相続開始後できるだけ早くに税理士に相談した方がよいといえます。
税理士の専門分野
1 税理士の業務
税理士の独占業務としては、税務代理、税務書類の作成、税務相談といったものが挙げられます。
また、独占業務以外にも記帳代行、資金調達、M&A、事業承継といった業務もあります。
2 税理士にも得意分野がある

税理士の独占業務に税務相談があると述べましたが、税務相談で取り扱う税金にもいろいろな種類があります。
法人税、所得税、相続税、贈与税、それぞれに異なった定めがあり、注意する点も違ってきます。
すべての税理士が、どの分野の税金にも詳しく経験豊富であることが理想ですが、実際には、医者が外科、さらにその中で、心臓外科、脳外科に専門が分かれていくように、税金の中でもそれぞれ得意分野があります。
得意分野でない税金の業務をしようとすれば、税理士であっても、慣れていないために処理が遅くなり、また、知識や経験が不足していることが原因で間違った処理をしてしまうこともあります。
3 税理士の得意分野が分かれる理由
このように特定の分野が得意な税理士がいる理由の一つとして、税理士になるための方法がいくつもあることが挙げられます。
税理士になる方法は、税理士試験に合格することだけではありません。
税務署に一定の期間勤務することでも、税理士資格を取得することができます。
税務署の多くの職員は、特定の税目を担当するため、その税目のスペシャリストになります。
そのため、担当していた税目については、知識、経験ともに豊富な税理士になるといえます。
この方法で税理士になった場合は、税務署の内情等を把握しているため、確定申告などの際に税務署での勤務経験を活かすことができます。
なお、税務署の職員の大半は、所得税、法人税を担当しており、相続税を担当する税務署は少ないといえます。
そのため、相続税に詳しい税理士も、他の税目に比べると人数が少ないといえます。
4 相談は経験豊富な税理士へ
これまで述べたように、税理士にはそれぞれ得意としている分野がありますので、税理士に相談する税目が決まっている場合は、その税目の扱いが得意な税理士に相談されることをおすすめします。
当法人では、それぞれの税理士が、特定の分野について経験を深めていく体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
税理士の選び方
1 税理士に依頼する際に見極める基準

税理士に依頼することを考えているものの、どの税理士に頼んでいいのか分からないと悩んでいる方も多いと思います。
税理士はどういった基準で選べばいいのでしょうか。
選び方にこれといった決まりはありませんが、いくつか見極める基準を説明していきたいと思います。
2 迅速な対応をしてもらえるか
税理士の仕事には、迅速な対応が求められます。
例えば、税務調査の連絡が税務署から来たため、税理士に相談をするというケースを考えます。
税務調査に効果的に対応するためには、税務調査の当日までに、納税者の申告の内容を数年分確認し、納税者と打ち合わせて、適切に問題点を把握する必要があります。
それができなければ、税務署の指摘を把握するだけで手一杯で、税務署へ反論することも難しいと考えられます。
また、税金の手続きには期限が定められていることが多いですが、突発的に対応しなければならなくなったという事案も珍しくありません。
こうした場合、当然に迅速かつ的確に処理を行うことが求められます。
こういったことからも、税理士には迅速に対応する能力が必要であるといえます。
3 税理士報酬が明確な税理士
もともと、税理士報酬は、税理士会によって税理士報酬規定が定められていました。
しかし、平成14年4月1日からその規定が廃止され、税理士報酬が自由化されたため、現在は各税理士事務所が自由に報酬を決めることができます。
ただ、中には、税理士報酬が分かりにくく、税理士業務が終わってから税理士報酬を請求し、しかも、その額が予想外の額になるというケースもあります。
したがって、税理士を選ぶ際には、明確な料金とどこまでの税理士業務を行ってくれるのかを分かりやすく提示してくれる税理士を選ぶことをおすすめします。
そういった税理士は、お客様の目線で物事を捉えることができ、提供するサービスの質も高いことが多いです。
4 税理士の選び方が分からないという方へ
上記のポイントは、税理士を選ぶポイントの一部です。
この他に、実際に税理士に会ってみて、ちゃんとコミュニケーションが取れそうな税理士かを確認することや、自分が求めるものを提供してくれる税理士かを慎重に検討することも重要です。
税金の申告で困った場合の相談先について
1 相談先は大きく分けて2つある

税金の申告を相談したいという場合、相談先は大きく分けて2つあります。
相談先としては、まず、税務署又は国税局が挙げられます。
例えば、税務署に電話をすると、国税に関する一般的な相談先として、各国税局に設置されている国税局電話相談センターに誘導され、各センターで相談内容を聞いてもらうことができます。
もう一つの相談先は、税理士事務所です。
ネット等で税理士を調べて電話をして、相談の予約をするというのが通常の流れです。
税務署又は国税局の場合は無料で相談することができますが、税理士に相談依頼する際には有料になる可能性が高いです。
2 税務署又は国税局で税金の相談をする場合
国税局電話相談センターでは、国税に関する一般的な質問、つまり税金に関する制度や法律等の解釈・適用についての相談に乗ってもらえます。
対応するのは国税局の職員です。
ただし、質問できるのは一般的なことにとどまり、個別具体的な相談には乗ってもらえませんし、申告書を代わりに作成してもらうということもできません。
次に、その相談者の方の住所地や事業所の所在地を所轄する税務署に、具体的な事実関係を説明した上で、相談することができます。
電話で相談することが難しい内容であれば、事前予約の上、税務署へ行って職員と直接相談することができます。
ただし、具体的事実に基づいた相談をしても、ここでは一般的な回答しか得られないことも多いようです。
また、電話相談と同様に、代わりに申告書を作成してもらうこともできません。
なお、税務署又は国税局では個人情報を確認されることは原則としてありませんので、匿名で税金に関する相談をしたい場合にはおすすめです。
ただ、税務署又は国税局は土日祝日に開庁していませんし、平日も夕方5時以降は開庁していませんので、平日にお仕事をされている場合は、相談すること自体が難しいかもしれません。
3 税理士に相談する場合
税理士には、個別具体的な事情をもとに相談することができ、さらには、具体的にどのように申告すればよいのかについても相談することができます。
具体的な請求書、通帳、領収書などを税理士に見せれば、かなり詳細な内容まで相談することができ、回答もより具体的なものになるかと思います。
税務署や国税局では、申告書作成の書き方や必要な添付書類の確認などを相談することしかできないのに対し、税理士は納税者の代わりに申告書を作成できるというのも大きな違いです。
申告書作成業務を依頼すれば、税理士は、資料をもとに仕訳を行い、帳簿作成、さらには、申告書の作成も行います。
特に、節税に関する相談については、税務署や国税局ではまず相談することができません。
税理士には、節税に関する相談等もすることができ、納める税金が最低限になるように利用できる特例等を検討してもらえます。
4 税金でお困りの方はご相談ください
税金で困った場合には、どのようなことを頼みたいかによって、相談する先が異なります。
質問に対して一般的な回答ではなく、具体的な回答が欲しい場合や、税金の申告を全部任せたいという場合であれば、税理士に相談することが適切と考えられます。
また、税理士事務所にもよりますが、税理士法人心では、事前の日程調整により土日祝日、また、夜間にもご相談をお受けすることができます。
税理士に依頼した場合の料金
1 税理士に依頼する際の料金の相場

税理士の料金の決め方は自由で、税理士事務所によって異なります。
事務所ごとに様々な料金の報酬体系があり、同じ業務であっても、かかる料金が異なることが多いです。
税理士が報酬体系を決めるにあたっては、日本税理士連合会の旧報酬規程を参考にしていることが多いです。
日本税理士連合会の旧報酬規定は、平成14年に廃止されていますが、今でも多くの税理士が参考にしていますので、ここでは、所得税の確定申告を税理士に依頼した場合を例に、どの程度の報酬となるか紹介していきたいと思います。
2 税務代理報酬と税理士報酬
税理士代理報酬は、依頼人の代わりに申告書を提出したり、税務調査になった場合に、調査の対応をしたりするための費用です。
税務代理報酬は事業規模等に応じて異なり、具体的には、以下のとおりとなります。
所得金額を基準とする場合
・200万円未満 60,000円
・300万円未満 75,000円
・500万円未満 100,000円
・1,000万円未満 170,000円
・2,000万円未満 255,000円
・3,000万円未満 300,000円
・5,000万円未満 400,000円
・5,000万円以上 450,000円
・1千万円増すごとに 2.5万円を加算
3 税務書類の作成と税理士報酬
申告書等の書類を作成するための費用も必要になります。
上記の税務代理報酬に加え、税務代理報酬額の30%相当額が確定申告書等の税務書類の作成報酬となります。
さらに、書面添付を行う場合には、税務代理報酬の20%が追加でかかるとされています。
書面添付とは、簡単にいうと、税金のプロである税理士が同じくプロである税務署の代わりに納税者を調査したということを明らかにし、税理士がどのような考えのもと、どのようにして申告書を作成したかという情報を書面に記載し申告書に添付して提出する制度です。
書面添付制度を利用した場合、いきなり税務調査が行われるのではなく、税務調査の事前通知を行う際に、意見を述べる機会が税理士に対して与えられるなど、納税者の負担を軽減できる可能性があるというメリットがあります。
4 その他追加の料金
確定申告は、毎年3月15日までに行わなければなりません。
そのため、2月や3月になってから依頼するとなると、申告期限まで間もなく業務量がひっ迫する可能性があることから、特急料金等が追加でかかる事務所もあります。
5 税理士報酬の注意点
税理士報酬は、どこまでの業務を依頼するかによって、そもそも金額が異なります。
他の税理士事務所と比べて安い税理士報酬を提示されたものの、そもそも、最低限の対応しかしてもらえないプランであったといったこともあり得ます。
したがって、税理士に業務を依頼する際には、見積もりで提示された税理士報酬で、どこまでの業務を行ってもらうことができるのか、しっかりと確認しておく必要があります。
税理士に相談する際に用意していただくとよいもの
1 資料があると具体的な相談ができる

税理士に税務相談する際は、単に、漠然と税金の相談をしたいということで、何の資料もなく、抽象的な話をするだけでは、本当に相談して解決したい疑問が解消できず、効率的な相談にはなりません。
具体的な資料に基づき相談した方が、どこをどのようにしたらよいかが明確になるため、より有意義なアドバイスを受けられるといえます。
具体的な資料がないと、推測での話にならざるを得ない場合もあり、場合によっては、前提としている事実が異なり、間違ったアドバイスをしてしまうことすらあり得ます。
あるとよい資料は、相談したい内容によって異なります。
ここでは、税務相談の際には、具体的にどのような資料を用意すればいいのか、説明をしていきます。
2 確定申告のご相談で用意していただくとよい資料
確定申告の目的は、その年の納付すべき税金の計算をすることにあります。
税金の計算のためには、売上から経費を差し引いた所得を算出する必要があります。
ですので、売上が分かる資料、つまり、請求書や売上の入金額がわかる通帳といった資料を用意していただくとよいです。
また、経費が分かる資料としては、領収書やクレジットの利用明細、レシートといった経費を支払ったこと及び金額が分かる資料を用意していただくとよいです。
なお、毎年確定申告をしている場合は、数年分の過去の申告書を用意していただくと、その年の売上と経費の金額をある程度具体的に推測することができ、スムーズに相談することができます。
3 相続税申告のご相談で用意していただくとよい資料
相続税の申告のためには、相続人の確定と相続財産の把握、財産の評価が必要になります。
相続人の確定のためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要になります。
また、相続財産については、例えば、預金通帳や株式の残高がわかる資料、毎年不動産の固定資産税の通知と一緒に送られてくる土地の固定資産評価明細書、保険金の支払通知書等を用意していただくとよいでしょう。
相続人の人数の確定ができれば、基礎控除額の計算を行うことができ、相続財産と評価をある程度具体的に行うことができれば、申告義務があるかどうかと相続税の概算の確認ができます。
4 用意する資料が分からない場合
このように、必要な資料は相談したい内容によって異なります。
税理士の相談の際に、何を用意したらいいのか分からないという方は、どんな相談をしたいのかを伝えたうえで、何の資料を持っていけばいいのか、事前に税理士にご確認ください。
税理士を紹介してもらう際のメリットと注意点
1 税理士を探す方法

税理士を探す際に、インターネットを使って、「岐阜 税理士」というワードで検索する方もいらっしゃるかと思います。
また、日本税理士連合会のホームページでは、「岐阜」という地域名で条件を絞り、税理士を検索することもできます。
他方、どんな税理士に依頼すればいいのか全く分からないという場合には、友人や知り合い等に税理士を紹介してもらうという方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、税理士を紹介してもらう際のメリットと注意点を説明していきたいと思います。
2 税理士紹介会社から紹介してもらう際のメリットと注意点
多くの税理士の中から、何の当てもなく探すとなると、かなりの時間と労力がかかってしまうかと思います。
また、日本税理士連合会のホームページの検索では、税理士会に登録されている税理士を探すことができますが、事実上、税理士業務を行っておらず、税理士登録だけしている方もいます。
税理士にどのようなサービスを求めるのか、費用感はどれくらいなのか等によって、選ぶべき税理士が異なるという点からも、適切な税理士を探すのは難しいといえます。
そのため、税理士紹介会社のサービスを利用すると、相談者からヒアリングをし、どのような税理士を探しているのか確認された上で、税理士とのマッチングがされますので、自分で探すより労力は少なくて済むという点ではメリットがあります。
税理士紹介会社を利用する注意点としては、紹介会社にも色々ありますので、実は紹介できる税理士が少なかったり、サービス内容やアフターフォローがいまいちの会社もあったりするということが挙げられます。
税理士紹介会社は、決まったフォームに沿って必要事項を聞き取り、複数の税理士に情報を共有し、紹介してほしいと手を挙げた税理士に相談者を紹介するという機械的な方法をとっていると思われます。
基本的に、相談者の一人一人に寄り添ってヒアリングをして、人格的に信頼できる税理士を紹介するという方法はとっていないため、適切なマッチングができるとは限らないということも注意すべき点です。
3 知り合いに税理士を紹介してもらう際のメリットと注意点
友人や知り合い等の紹介で税理士を探す場合には、紹介者である方自身の評判にも関わることになるので、税理士の能力に問題があったり、人格に問題があったりする可能性は低く、一定レベル以上の税理士であることが期待できます。
しかし、紹介者の方もその税理士に相談している場合には、その方と自分の相談内容が同じであるとは限らないため、自分の相談したい内容について詳しい税理士ではないこともあり得ます。
そのため、注意点として、税理士にはそれぞれ得意分野があり、ニーズが一致しない場合もあり得ることが挙げられます。
その場合は、しっかりと理由を話した上で断れば問題ありません。
まずは税理士と話をしてみた上で、自分に合ったより良い税理士を選ぶのがよいといえます。
確定申告と医療費控除
1 医療費控除とは

医療費控除というのは、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定金額以上になった場合に、その医療費の一部について、所得から控除できる制度です。
ここでいう医療費には、自分のために支払ったものだけでなく、扶養家族のために支払ったものも含まれます。
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金等の金額と10万円(所得が200万円未満の場合は、所得金額等の5%)を差し引いた額で、最大200万円まで所得控除されます。
ここでいう保険金等は、民間の保険で支給される入院費給付金や健康保険等で支給される高額療養費、出産一時金等のことをいいます。
ただし、保険金は、給付の目的となった医療費の金額を限度に差し引くため、医療費よりも保険金の方が高額だったとしても、それ以外の医療費から差し引くことはありません。
また、医療費控除は10万円以上の医療費を支払っていないと意味がないと思われている方も多いですが、その年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%以上の金額を支払っていれば、医療費控除を受けることができますので、損をしないように注意が必要です。
なお、知らない方もいらっしゃるかと思いますが、病院に行くための交通費も医療費控除の対象となるため、いつどこの病院に行くためにどの交通機関でいくら支払ったのか、資料を残しておくようにしてください。
2 領収書の提出の必要性
医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。
平成28年分以前の確定申告書を提出する場合には、医療費の領収書を確定申告書に添付、又は提出の際に提示しなければなりませんでした。
しかし、領収書の添付や提示というのは、大量に領収書がある場合には、税務署にも納税者にもかなりの負担となっていました。
そこで、平成29年度税制改正では、この手続が見直され、平成29年分以後は、医療費控除の明細書を作成して、確定申告書に添付すれば、領収書を提出しなくていいことになりました。
さらに、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合には、医療費控除の記載を省略できることになり、かなり手続きが簡略化されたといえます。
3 医療費の領収書の保存が必要
医療費の領収書の添付も提示もしなくてよくなりましたが、領収書を保存する義務がありますので、注意が必要です。
確定申告期限から5年を経過する日までの間は、医療費に関する領収書を保存しなければなりません。
通院のための交通費で領収書がない場合は、病院へ行った日時、利用した交通機関、交通費の金額のメモを残しておくようにするとよいです。
税務署が、医療費に関する領収書の提示又は提出を求めてきた場合に対応できるよう、しっかりと保管しておくことが重要です。
4 お気軽にご相談ください
確定申告など、税に関する手続きが適切に行えるかどうかご不安な方もいらっしゃることと思います。
ご心配な方は、当法人の税理士までお気軽にご相談ください。
遺言について税理士がかかわる重要性
1 遺言と税金

遺言は、遺言者の財産について、どの財産ををどのように相続等をさせるかということを記載するものですので、遺言を作成すること自体で、税金が安くなるという制度はありません。
ただし、税理士が関わることで相続税の適切な申告、円滑な遺産分割といっったことが実現できます。
例えば、税理士が誰に何を相続等をさせるかアドバイスすることによって、税務署に納める税金を低く抑えることのできる相続税の特例の適用が受けられるなど、税金にも配慮した遺言を作成できることが期待できます。
遺言を作成したことにより小規模宅地等の特例を適用することができ、税金をかなり抑えることのできる場合について、説明していきたいと思います。
2 小規模宅地等の特例と遺言
被相続人が相続開始時点で居住していた土地、事業に使っていた土地、人に貸していた土地等は、一定の要件のもと、相続税評価額を減額できるという特例があります。
土地という大きな財産の相続税評価額を減額できると、かなり税金を引き下げることができます。
具体的には、土地の評価額を、一定の面積まで、最大8割減額することができます。
被相続人が居住していた宅地の場合は330㎡、つまり約100坪の面積まで相続税評価額を8割減額することができます。
この小規模宅地等の特例を用いるためには、一定の条件を満たす必要があります。
その条件の一つとして、配偶者又は被相続人と同居していた親族等、一定の親族が宅地を取得する必要があります。
遺言がない場合には、相続人全員で分割協議を行い、誰が宅地を取得するか確定させなければ、この特例は適用できないことになります。
また、複数の土地がある場合、小規模宅地等の特例を用いるためには、その特例の適用の可能性のある土地を取得した相続人全員の同意が必要になるので、その同意が得られないと特例の適用ができないことになります。
他方、生前に遺言書を作成して土地を誰が取得するかを確定させておけば、分割協議をすることなく、小規模宅地等の特例の適用が可能な状況を用意しておくことができます。
逆に、遺言書がなく、相続人間で相続財産の分け方で揉めてしまい、誰が宅地を取得するか確定しない状況では特例の適用はできないことになります。
こういった税金に関する特例を意識してアドバイスができるのは、税理士であるといえます。
3 どのような税理士に相談するべきか
このように税理士は、税金のことを意識して、遺言書の内容をアドバイスすることができ、その結果、相続税の額が大きく変わる可能性があります。
ただし、遺言には法律の専門家のアドバイスも必要となってきますので、法律の専門家と連携している税理士に相談をしましょう。
顧問税理士とは
1 顧問契約と税理士

顧問税理士とは、一定期間において法人又は個人事業主と顧問契約を結んだ税理士を指します。
顧問契約は、1年契約で、自動更新されるという内容になっていることが多いです。
毎年、顧問契約書を締結し直しているという方は、かなり少ないのではないでしょうか。
顧問契約と一言でいっても、その内容は契約次第なので、顧問税理士の役割は様々であるといえます。
法人又は個人事業主は、税理士と顧問契約を結ぶことで何をしてもらうことができるのか、確認しておくことが大切です。
顧問税理士の役割としては、税務申告のサポート、記帳代行、決算書作成、税務調査への対応、経営支援等があり、顧問先の健全な経営や税務リスクを最小化することが重要となります。
どこまでの役割を求めるか、事業の規模、業界によって、顧問料も変わってきますので、どこまでの業務を依頼するとどの程度の顧問料となるのかを事前に確認されるとよいでしょう。
2 顧問税理士のメリット
税理士に仕事を依頼する方法として、大きく分けて単発のスポット契約と継続的な顧問契約の2つに分かれます。
スポット契約のメリットは費用の安さです。
確定申告のみ、決算申告のみといった単発あるいは限定的な仕事を税理士に依頼するので、税理士報酬を抑えることができます。
他方、顧問契約は、一年を通して会計や税務のサポートを税理士が行う契約になるので、毎月顧問料が発生します。
しかし、月次の試算表を作成してもらうことで、経営状態を定期的にチェックすることができますし、税務のプロに、事業のうちの会計や税務の部分を任せることで、本業に専念することができます。
3 顧問税理士の見つけ方
顧問税理士とは、長期的な関係を維持していくことが一般的であり、顧問先のニーズや目標を理解し、適切に対応してくれることが重要な要素といえます。
顧問税理士を探す方法として、知人の紹介というものがあります。
知人が紹介してくれるようなお勧めの税理士であれば、信頼できる税理士を見つけることができる可能性が高いです。
しかし、信頼できることと求めている能力があることは別の問題です。
その知人と紹介を受けた方が異なる税務サービスを求めていた場合には、信頼できる税理士であったとしてもミスマッチな結果となってしまいます。
インターネットで税理士を探す場合には、その税理士の得意分野や料金体系、サービス内容をホームページで確認しましょう。
そして、実際にそうだんをしてみて、コミュニケーションが円滑で、継続的に信頼関係が築ける税理士かどうかを意識して選ぶことが重要です。
税に関する情報
税や税理士へのご相談に関する各種情報をご覧いただけます。ご参考にしていただくとともに、何かお悩みのことがありましたら当法人の税理士にご相談ください。