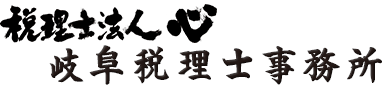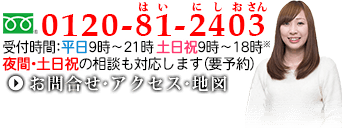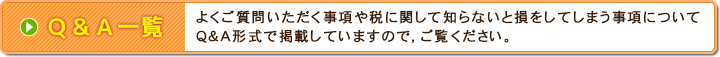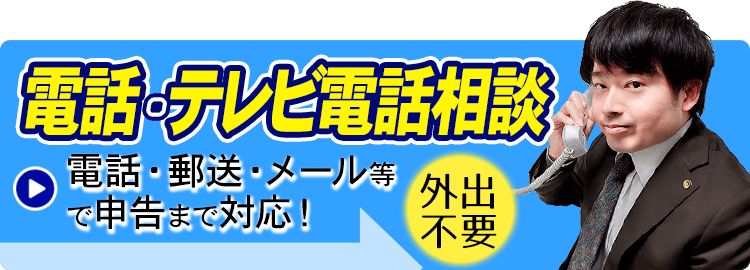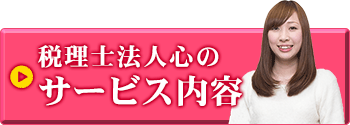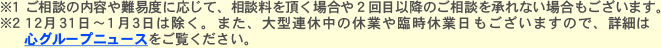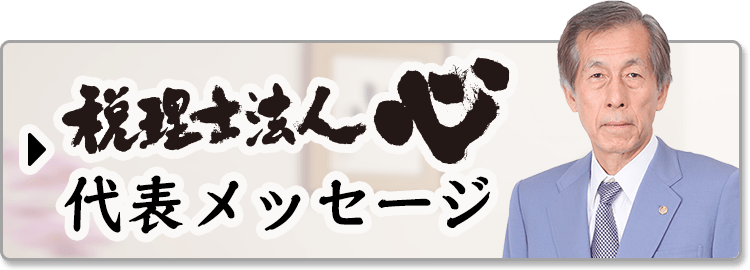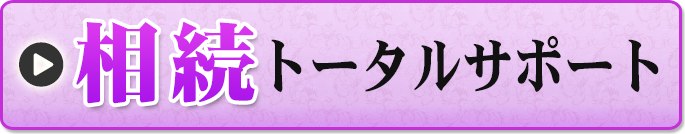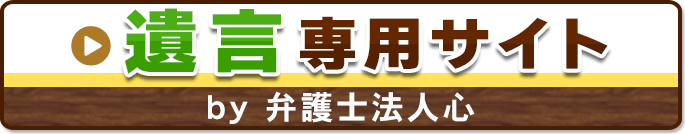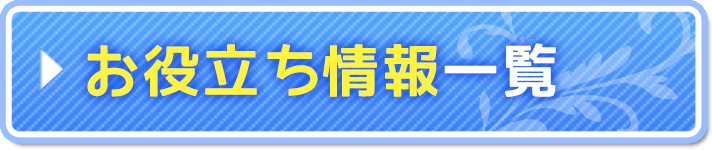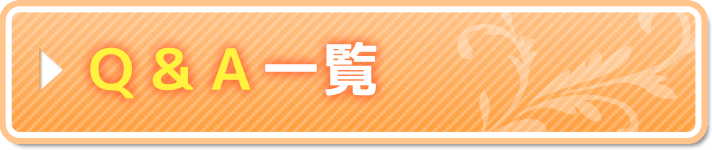所得税における控除の種類
1 日本の居住者が利用できる所得税の控除は15種類
- ① 雑損控除
- ② 医療費控除
- ③ 社会保険料控除
- ④ 小規模企業共済等掛金控除
- ⑤ 生命保険料控除
- ⑥ 地震保険料控除
- ⑦ 寄付金控除
- ⑧ 障がい者控除
- ⑨ 寡婦控除
- ⑩ ひとり親控除
- ⑪ 勤労学生控除
- ⑫ 配偶者控除
- ⑬ 配偶者特別控除
- ⑭ 扶養控除
- ⑮ 基礎控除
2 日本の非居住者が利用できる所得税の控除は3種類
- ① 雑損控除
- ② 寄付金控除
- ③ 基礎控除
3 所得控除と税額控除は異なることに要注意
よく、所得控除の額がそのまま税金の金額から差引かれると思われている方がおられます。
税金の金額から直接差引かれる控除は、「税額控除」であり、「所得控除」とは別の控除となります。
所得控除は、あくまでも税額計算の元となる所得金額から差引かれるにすぎません。
ですので、税額が安くはなりますが、所得控除の金額そのものが税額から差引かれるわけではないことに注意が必要です。
4 所得控除の内容
⑴ 雑損控除
災難・盗難などで資産に損害を受けた場合に一定程度の所得控除を受けることができる控除です。
⑵ 医療費控除
1年間の間に支出した医療費の額について、一定程度の所得控除を受けることができます。
⑶ 社会保険料控除
健康保険料や国民年金・厚生年金などのいわゆる社会保険料を支払った場合に、所得控除を受けることができます。
⑷ 小規模企業共済等掛金控除
一定の要件を満たす小規模事業者が支払った掛金について、所得控除を受けることができます。
⑸ 生命保険料控除
ご自身が加入している生命保険、介護保険、年金保険などの民間の保険会社に対する保険料について、一定額を限度として所得控除を受けることができます。
⑹ 地震保険料控除
ご自身の自宅について地震保険に加入している場合に、その保険料について受けることのできる所得控除です。
ご自身が賃貸物件を経営されている大家さんなどの場合には、その物件の地震保険は、不動産所得の経費とはなりますが、地震保険料控除の対象とはならないことには注意が必要です。
⑺ 寄付金控除
国や自治体等から指定された一定の機関に対して寄付を行った場合に受けられる控除です。
ふるさと納税が代表的な例といえます。
⑻ 障がい者控除
ご自身やご家族が障がい者の場合に受けられる控除です。
障がいの等級や同居の有無等によって、受けられる所得控除の金額が異なります。
⑼ 寡婦控除
ひとり親控除に該当せず、夫と離婚や死別した後、婚姻をしておらず、合計所得金額が500万円以下の人等が対象の控除です。
⑽ ひとり親控除
婚姻をしていない又は配偶者の生死が不明で、事実婚相手もおらず、生計を一にする子どもおり、合計所得金額が500万円以下の方が対象となる控除です。
子どもの所得金額やその子どもが他人の扶養家族などになっていないことも要件としてみられます。
⑾ 勤労学生控除
納税者が「勤労学生」の要件にあてはまる場合に受けられる控除です。
「勤労学生」の要件として、合計所得金額が75万円以下で、それ以外の所得が10万円以下であることや、特定の学校の学生・生徒であることが要件となっています。
⑿ 配偶者控除
納税者に「控除対象配偶者」がいる場合に受けられる所得控除です。
注意が必要となりますのは、法律上の配偶者でなければならず、事実婚や内縁、自治体のパートナー婚などは対象となっていません。
また、配偶者の方が青色事業専従者や白色事業専従者になっていないことなども要件となっています。
⒀ 配偶者特別控除
配偶者が「配偶者控除」が受けられないほどの所得金額がある場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられることがある制度です。
⒁ 扶養控除
納税者が一定の親族を扶養している場合に、一定金額の所得控除を受けられる制度です。
⒂ 基礎控除
納税者本人の合計所得金額が2500万円以下の場合は、受けられる控除です。
2400万円以下は48万円、2400万円超2450万円以下は32万円、2450万円超2500万円以下は16万円になります。
この48万円の基礎控除額が、令和7年税制改正によって10万円上乗せされ、58万円となります。